大河ドラマ『べらぼう』の“攻めた”表現
- 第18話で「番組の一部に性に関する表現があります」と冒頭に異例のテロップを入れたのは、NHKにとってかなり挑戦的な試みといえます shueisha.online+2minpo.online+2onecareer.jp+2trendailys.net+2bunshun.jp+2president.jp+2。
- 歴史評論家・香原斗志氏も「性に関する表現を避けず正面から取り上げたのは、この時代の描写として真っ当…NHKがこれを許したことには価値がある」と評価しています bunshun.jp+1president.jp+1。
- 喜多川歌麿が幼少期に遊郭で働かされた過去やEDを含むコミカルな性描写など、コメディとシリアスを巧みに織り交ぜ、視聴者に強い印象を残しています shueisha.online+4lmaga.jp+4trendailys.net+4。
→ 特に“性”を扱う内容で前例のない注意テロップを導入したあたり、公共放送らしい慎重さと一方で果敢に挑戦する姿勢がうかがえます。
“俗っぽい”文化をどう表現するか
- アニメや俗文化の取り込みでは、NHKは民放とは異なる“高い公共性”と“教育性”の両立を意識しています。
- 『べらぼう』では遊郭の煌びやかさと陰惨さという相反する文化要素を両方描くことで、ただの娯楽ドラマではなく“教養を伴った娯楽”へ昇華させているように見えます shueisha.online。
- 「遊郭」という題材は、これまで一般放送では敬遠されてきたものですが、民放では『鬼滅の刃』遊郭編のような人気アニメがあり、それに対しNHKとしては地域文化や歴史の深堀りで独自性を出している点に注目です shueisha.online。この点を少し深掘りしてみます。
背景:『鬼滅の刃 遊郭編』のヒットと“俗文化”の受容
『鬼滅の刃』遊郭編は、2021年〜2022年に放送され、日本のテレビアニメ史上でも非常に高い評価と視聴率を誇る作品でした。この「遊郭」という題材は、歴史的には江戸の色街文化であり、“性”や“欲望”がテーマに絡むため、これまで一般放送では敬遠されてきたものです。
しかし、作品では“女性の強さ”“差別の克服”“家族愛”などを描くことで、遊郭をただの“性の場所”としてではなく、歴史的・文化的背景をもつ舞台として成立させました。
その結果、「俗(ぞく)」と思われがちな遊郭文化が、“娯楽作品の中でも教養的に受け止められる”流れができたのです。
NHKの立ち位置:文化を「知的エンタメ」に昇華
この流れに対して、NHKは次のような戦略を取っているように見えます:
“似た題材”でもアプローチは全く違う
NHKの大河ドラマ『べらぼう』でも遊郭が描かれますが、アニメのような娯楽性よりも、史実に基づいた社会的・文化的分析に重きを置いています。
- 例:「吉原の制度」「遊女の身分制度」「性がどう管理されていたか」「浮世絵と性文化の交差点」など。
ここには「視聴者に“知ってほしい歴史”としての遊郭」があります。
公共放送だからこそ描ける“深堀り”
NHKは、娯楽としてのアニメや民放のドラマと一線を画し、
- “歴史の影にある真実”
- “現代社会と繋がる構造”
- “当時の人々のリアルな暮らし”
など、いわば“文化資産の再解釈”として番組を作っています。
たとえば、2024年のBS放送やNHKスペシャルでは「遊郭と近代のジェンダー問題」や「浮世絵と庶民文化」といったドキュメンタリーも展開されており、これは娯楽の延長ではなく、知的探究心を刺激するものです。
要するに:NHKは「俗」すらも“学びの素材”に変える」
『鬼滅の刃』のようなコンテンツが大衆を惹きつけるなら、NHKはその流れを無視せず、
「それを深く知る機会を提供する」
という立場をとっていると考えられます。
つまり――
| 民放やアニメ | → 「遊郭=舞台としての刺激」 |
| NHK | → 「遊郭=社会的意味と制度の歴史」 |
このように、「テーマは同じ」でも、「問いの立て方」が異なるのです。
関連する今後の展望
NHKは今後も、
- Z世代への文化伝承
- 歴史の“光と闇”の再提示
- ジェンダーや差別の構造的考察
といった分野で、俗文化やポップカルチャーを“学術的視点”で発信する戦略を強めると予想されます。
たとえば:
- NHK for School → 若年層向け歴史再現アニメ
- NHK BSプレミアム → 文化の舞台裏を描くドキュメンタリー
機会があれば、今後、以下のような分野についてNHKの立ち位置や報道思想、手法など少し深掘りしていきたいと思います。
- NHKが制作した“性・ジェンダー・差別”を扱うドキュメンタリーの歴史
- 民放とNHKの“娯楽”と“教養”の役割の違い
- NHKがアニメやサブカルにどう向き合ってきたか(例:『精霊の守り人』『岸辺露伴』)
おわり
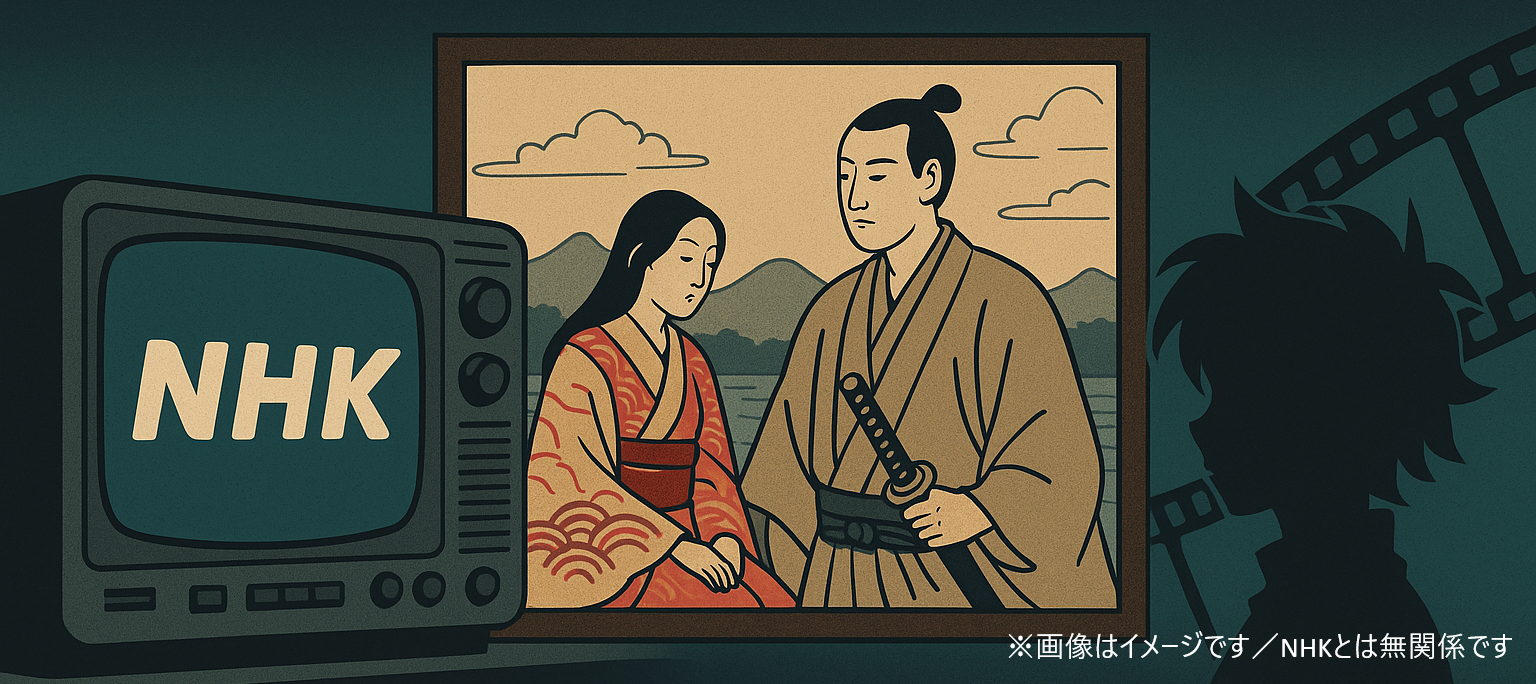
 風4png-120x68.png)
風 5-120x68.png)
コメント